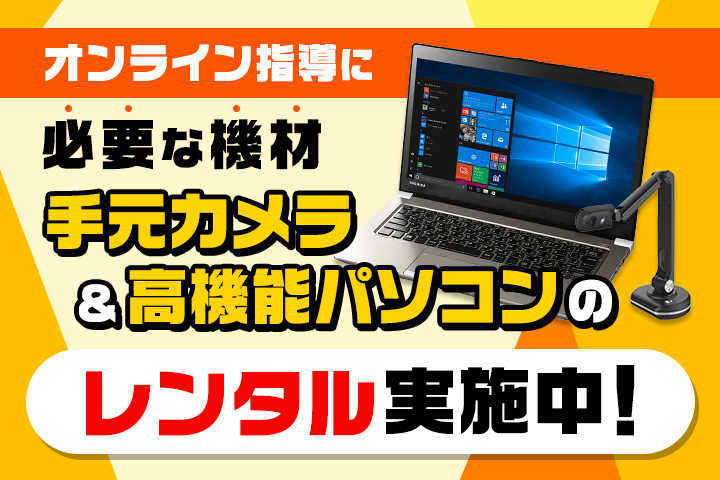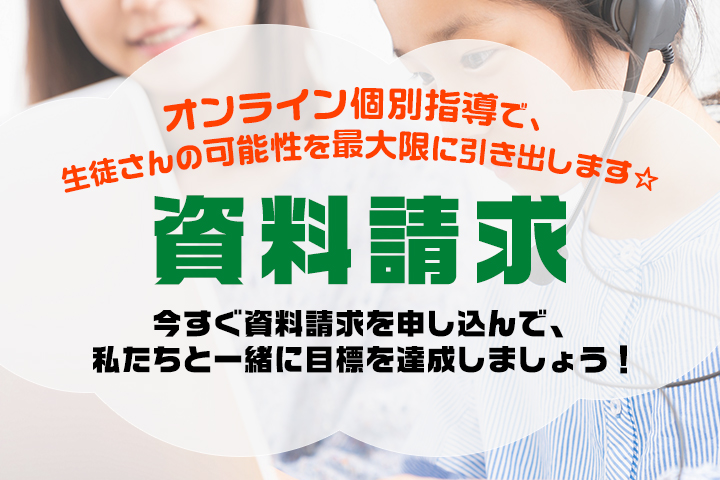■問題PDF
令和7年度_学力検査問題過去問【神奈川】-国語
■目次
大問1
大問2
大問3
大問4
大問5
■大問1
] 次の問いに答えなさい。 (ア)次のa~dの各文中の 線をつけた漢字の読み方として最も適するものを、あとの1~4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。
a 友人から頻繁に連絡がくる。
(1 はんざつ 2 ひんばん 3 はんも 4 ひんど)
b 彼の発表に聴衆が喝采を送る。
(1 かっとう 2 かっさい 3 けいさい 4 けいとう)
c 武道場で竹刀の手入れをする。
(1 ぼくとう 2 ちくば 3 しない 4 めいとう)
d 行事の内容を生徒会に諮る。
(1 はか 2 つめ 3 ゆず 4 せま )
解答 : a:2 b:2 c:3 d:1
(イ)次のa~dの各文中の――線をつけたカタカナを漢字に表したとき、その漢字と同じ漢字を含むものを、あとの1~4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。
a 会社からキュウリョウが支払われる。
1 彼とは同じ学校にと通ったキュウチの間柄だ。
2 矢を射る姿に憧れてキュウドウを始める。
3 飛行機に乗ってキュウシュウへ行く予定だ。
4 昼になり教室までキュウショクを運ぶ。
b 商品がすぐに完売したのはうれしいゴサンだ。
1 集会が終わってカイサンする。
2 多くの生物は生きるためにサンソが不可欠だ。
3 妹がサンスウの勉強をしている。
4 繭をとるために行われるのがヨウサンだ。
c 小学生がvシュウダンで登校する。
1 オンダンな気候を生かした農業を行う。
2 月を見ながらダンゴを食べる。
3 休み時間にザツダンをする。
4 今年の新入社員はダンセイの人数が多い。
d 監督が選手をヒキいて大会に臨む。
1 仕事のノウリツを上げる。
2 現場で安全確認をテッテイさせる。
3 社会の授業でホウリツについて学ぶ。
4 無理をしないことが山登りのテッソクだ。
解答 :a:4 b:3 c:2 d:1
解説 :
a. 会社からキュウリョウが支払われる。
「キュウリョウ」は「給料」と書きます。「給」という漢字が含まれる選択肢を探します。
1 旧知
2 弓道
3 九州
4 給食
b. 商品がすぐに完売したのはうれしいゴサンだ。
「ゴサン」は「誤算」と書きます。「誤」という漢字が含まれる選択肢を探します。
1 解散
2 酸素
3 算数
4 養蚕
c. 小学生がシュウダンで登校する。
「シュウダン」は「集団」と書きます。「団」という漢字が含まれる選択肢を探します。
1温暖
2 団子
3 雑談
4 男性
d. 監督が選手をヒキいて大会に臨む。
「ヒキいて」は「率いて」と書きます。「率」という漢字が含まれる選択肢を探します。
1 能率
2 徹底
3 法律
4 鉄則
(ウ)次の俳句を説明したものとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい
〈天心の月の左右なる去年今年 井沢正江〉
1 大みそかの夜に空の中心で輝く月に注目しつつ、まるで自分自身が去年と今年の間を「左右」に行き来しているようだと表現することで、年の瀬のあわただしさを強調して描いている。
2 この一年間で見た「天心の月」の美しさを思い出しながら、大みそかに去年から今年へと年が移り変わっていくのを味わったということを、体言止めを用いることで印象的に描いている。
3 空の左側から昇った月が空の中心を通り右側に沈むのを見届けた後に、今度は年が替わっていくのを感じ取ろうとするさまを、「去年今年」という季語を用いることで効果的に描いている。
4 大みそかの一夜にして去年から今年へと年が替わるという時の推移を、「左右なる」という表現によって、空の真ん中に浮かぶ月を中心とした空間の中で捉えることで壮大に描いている。
解答 : 4
解説 :
1 この解釈は、「左右」を作者自身の行き来に結びつけており、年の瀬の慌ただしさを強調している点が少しずれています。俳句全体としては、時の移り変わりを静かに捉えるニュアンスが強いです。
2 「天心の月」の美しさを一年間思い出すという点は、句の直接的な内容とは少し異なります。「去年今年」は年の境目を指す季語です。
3 月の動きを左から右への具体的な時間の経過と捉えるのは、やや物理的すぎる解釈です。「天心」は空の真ん中を指し、その位置で月が輝いている状況です。
4 この解釈が最も適切です。「天心の月」は空の真ん中に堂々と輝く月を指し、その月を基準として、「左右なる」という表現が、時の流れ(去年から今年へ)が広大な空間の中で行われているかのように感じられることを示しています。つまり、移り変わる時間を、月の位置する広大な空間の中で捉えることで、時の移ろいの壮大さ、悠久さを表現していると言えます。
したがって、最も適切な説明は 4 です。
■大問2
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
[ 大学生の「僕(青山)」は水墨画家であり、小学校から依頼されて一年生のクラスを対象にした水墨画教室の講師を引き受けた。筆を使って絵を描かせた初回の授業では、子どもたちの中でも特に「水帆」が楽しんで課題に取り組んでいた。後日、二回目の授業で、「僕」は筆の代わりに指を用いる指墨画という描き方で、シイタケを描かせることにした。 ]
全員が、千差万別、無限の変化をするシイタケの究極の形を探しているようにも思えた。水墨画というのは、もしかしたらこういうふうに発展したのではないかとさえ思ってしまう。僕は次々に子どもたちの作品をピックアップしていった。
みんな違う。そして、描き始めれば、それぞれが比べようのない個性なのだと分かる。椎葉先生はこのことを言っていたのだなと思い至った。慣れてきたところで、僕も少しずつ助言をはじめて、なるべく手が止まらないように指導した。
いつのまにか子どもたちの中に、年配の女性が一人混じって指墨を始めている。年季の入ったデニム地のエプロンを着けていて大量の染みや汚れがついている。ペンキか絵具か墨か、ともかく夥しい汚れが模様に変わっているエプロンだった。他のクラスの先生かもしれない。僕が驚いて見つめていると、
「青山先生、私も教えて下さい。」
と品のよい声で促された。状況はよくわからなかったが、子どもたちに与えているものと同じような助言を彼女に与えることにした。
「形は思うままに描いて下さい。この通りじゃなくてもいいんです。描きながら、楽しそうだと思うほうに手を動かして下さい。新しいやり方をみつけたら、それを試してみて下さい。紙はいっぱいあるんだから。」
そんなことを、相手の動きを見ながら伝える。彼女は絵画の心得があるようで、目の前にあるシイタケの形を意識して綺麗に描いていた。その分、線に少し面白みがない。器用すぎるのだ。1僕はシイタケを取り上げた。彼女は驚いた。僕は微笑んだ。
「形ではなくて、心に浮かんだものを、今度は描いて下さい。」
そう言うと、彼女は大きく微笑み、
「青山先生、ありがとうございます。」
と深く頭を下げた。僕はその仕草にあたふたしてしまった。驚いた僕を視界から外し、彼女は描き始める。僕はその姿を見て取り、次の席に移動した。目の前に、大苦戦を強いられている子がいた。
水帆ちゃんだ。
手が止まっている。何枚か描いたようだけれど、どれも小さく生き生きとしていない。僕が傍に来たときも首を傾けて、つまらなそうに紙を見ていた。僕は彼女の目線に目を合わせるため屈んだ。
「水帆ちゃん、どうしたの?」と誘ねると、2眉をひそめた。話す気はないようだ。筆を持てないことと、うまくいかないことがつまらないのかもしれない。
「指墨画は面白くないかな。」コクンと頷く。「どうして?」と訊ねると、
「きれいな線じゃない。」と言った。僕は思わず微笑んでいた。この子の心は絵師なのかもしれない。
「僕も最初はそう思った。でも指墨画をやっているうちに、これは絵を描いていく上ですごく大切なことをいっぱい勉強できるなあって思ったよ。先生と一緒に少しだけ描いてみよう。」
彼女はまた無表情のままこちらを見ていたけれど、僕が微笑むとやっと頷いてくれた。
「じゃあまず普通に描いてみよう。」
僕は彼女の前にシイタケを置いた。彼女はそれをじっくりと観察したあと、指先に墨を浸けるとサッと線で描いた。面白みのない円と軸が二筆で描かれた。他の彼女が描いたものとほぼ同じだ。
「同じ。」彼女はボソッと言った。つまらない、という意味だろう。たぶん物足りないのだ。あれだけ筆を使う楽しみを感じていた子なら当然かもしれない。
「じゃあ次に、ちょっと手を洗ってみて。」
僕は筆洗に入った綺麗な水で手を洗うように指示した。真新しい布巾で水分を拭い、指先はさっきよりも綺麗になった。僕はシイタケを手渡した。
「指先で触ってみよう。」
彼女は小首をかしげた。何を言っているんだ、という表情だった。そして、
「見たものを描くんじゃないの?」と訊ねた。
僕は首を振った。 僕は微笑んだ。
「目で見たものを描くなら、見てるだけでいい。でも、手で触れた感触はどうやって描く?」
しばらくして、彼女はハッとしたように言った。彼女は瞳を輝かせながら、
「手で触る。」とはっきり言った。その答えが欲しかった。僕は本当に微笑んだ。子どもと一緒にいるときにだけ現れる「伝わる」という感覚だった。
「そうだよ。手で触った感触を描くには、触るしかない。目で見たものだけが、絵になるんじゃないんだ。 形だけが絵になるんじゃないんだよ。目には見えないものさえ絵になるんだ。」
彼女はうんうんと何度も頷き、シイタケに触れた。小さな指先で、襞に触れ、笠に触れ、軸に触れ、石づきに触れた。3笠の周囲のでこぼこに触れたとき、大きく目を見開き、光にかざしてシイタケを全体から眺めた。
これこそが、おそらく子どものころの湖山先生が師に指墨を遊びとして授けられた意味なのだろう。彼女はもう一度、シイタケの全体に触れる。すると、こちらを見向きもせず指に墨を浸けて絵を描き始めた。
絵が変わった。
筆致は遅くなり、墨つぎは増え、線はでこぼこになった。形はさっきよりも歪で、整わなくなった。けれども、さっきよりも面白味があり、生き生きとしたものになった。僕は微笑んだ。
彼女はさらにそこに水を足して、墨をボケさせ、笠を完成させると軸を描き、濃墨で、軸の切れ目の石づきを塗った。墨面にかすれを与えるために布巾に墨を吸わせることまで思いついていた。
絵には明らかに形以上のものが描き加えられていた。形を超えたものを表現しようとしていたといってもいいかもしれない。
彼女の感覚が絵の中にはあった。
「手で触れてみてどうだった?」と僕は水帆ちゃんに訊ねた。すると、
「でこぼこだ!」と、また大きな声で答えた。僕はまた嬉しくなった。4これまで感じたことのない喜びだった。
簡単な言葉だけれど、そうじゃない。彼女が描いたのは、でこぼこ以上のものだ。そして彼女が指先で触れて感じ取ったものは、言葉にはしようのない複雑な感覚や、もっといえば生命感そのものだ。それが、またた瞬く間に、小さな指先から絵になった。
それを描出しようとすることで、より深く感じ取り、一つにまとめようとすることで新たに感覚を生み出す。惜しみなく、彼女はそこに注ぎ込まれていく。それは、絵を描く喜びだった。喜びがたった一個のシイタケに溢れていた。この直截性は、筆ではとても再現が難しい。けれども、指先なら誰でもが達人のような感覚で描くことができる。 「気韻生動………………。」と僕の口から、思わず言葉がもれた。
「きいん、せいどう・・・・・・?」と彼女は言葉を繰り返す。その拙い声の響きが、また僕に大切なことを教えてくれた。
「言葉なんてどうでもいいんだよ。生き生きとした線を引くことや絵を楽しむことが、一番大事だってことだよ。僕も昔、それを教えられたんだ。ずっと忘れていたけどね。」
「先生でも忘れることがあるの。」
「忘れちゃうよ。どんな大切なこともね。」
彼女が澄んだ瞳でこちらを見て微笑んだ。大人が微笑むときのようだった。彼女の知性が微笑んだのか「じゃあ、私がときどき思い出させてあげるね。」
彼女がその日一番、優しく微笑んだ。
(砥上裕將「一線の湖」から。一部表記を改めたところがある。)
(ア):線1「僕はシイタケを取り上げた。」とあるが、その理由として最も適するものを次の中から一 つ選び、その番号を答えなさい。
1 簡単な助言を受けただけで、形にこだわらずに描くことの重要性を理解した「年配の女性」の様子を見て、シイタケを回収して一旦手を止めさせた上でより高度な内容の指導をしようと思ったから。
2 子どもたちのために絵を描く際の見本としてシイタケを持ってきたのであり、「年配の女性」が知らない間に授業に参加して、何も言わずにシイタケを使っていたのをやめさせたいと思ったから。
3 描く対象を見て形を整えて描くという考え方に縛られず、楽しんで心のままに描けばよいということを「年配の女性」に実感してもらうために、形にとらわれすぎないようにさせたいと思ったから。
4 面白みのない線を描く傾向が「年配の女性」にあることを見抜き、実物を手で持ち上げる動作を目の前で行うことで、描く対象を見るだけでなく触れる必要があることにも気づかせようと思ったから。
解答 : 3
解説 :3が適切: 女性は形にとらわれていたため、そこから離れ、心に浮かんだものを自由に描くよう促したかったからです。
1が不適切: 女性がすでに「形にこだわらずに描く重要性」を理解した描写はありません。
2が不適切: 女性の参加を拒否する意図はありませんでした。
4が不適切: 「触れる」指導はこの女性ではなく、水帆ちゃんに行われました。
(イ):線2「眉をひそめた。」とあるが、そのときの「水帆」を説明したものとして最も適するものを 次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 指墨画では自分が描きたいような線を描けないからつまらないと感じており、「僕」に訊ねられたときに自分の気持ちが言葉としては表されなかったが、表情に心の内が出ている。
2 思ったような表現ができず早く指墨画の描き方を教わりたいと思っていたのに、「僕」がなかなか自分のもとに来なかったので、不満を言葉にはしていないが表情で示している。
3 筆と違って指では納得のいく表現ができず、きれいな線にすることを目指し真剣に絵を描いている最中に「僕」に質問されて集中を妨げられたため、不服そうな顔つきをしている。
4 指ではうまく描けないことを自覚して落ち込んでいたときに、線が美しくないことを「僕」に批判されたため、自分の思いをわかってもらえず残念に思う気持ちが顔に表れている。
解答 : 1
解説 :1が適切: 指墨画で描きたい線が描けず、つまらないと感じていた気持ちが表情に出ていたからです。
2が不適切: 僕がなかなか来ないことへの不満の描写はありません。
3が不適切: 彼女は集中して描いている最中ではなく、手は止まっていました。
4が不適切: 僕から絵を批判されたわけではありません。
(ウ):線3「笠の周囲のでこぼこに触れたとき、大きく目を見開き、光にかざしてシイタケを全体から眺めた。」とあるが、そのときの「水帆」を説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、 その番号を答えなさい。
1 シイタケを触る中で、目で捉えていなかった笠の周囲のでこぼこに気づいて心が動き、光に照らし シイタケがどのようなものなのか感性によってつかむことで、絵に表すものを見いだそうとしている。
2 シイタケに触れた結果、笠の周囲のでこぼこが想像していたものと違うということがわかって驚くとともに、明るいところでよく見てシイタケの形を正確に捉え、絵の精度をより高めようとしている。
3 シイタケを触ることで、見つけてはいたが気にしていなかった笠の周囲のでこぼこを再確認した結 果、見えるものはすべて描こうと考えて、光と重ねながらシイタケの特徴を把握しようとしている。
4 シイタケに触っただけでは、笠の周囲のでこぼこの存在に気づくことができなかったため、シイタケの本質について明るい場所で触覚と視覚を交えながら把握し、新たな表現を生み出そうとしている。
解答 : 1
解説 :1が適切: 触覚で目に見えない新しい発見があり、それがきっかけで、単なる形ではなくシイタケの本質を感性で捉え、表現しようとしたからです。
2が不適切: 単に「正確に形を捉える」ことが目的ではありません。
3が不適切: 「見つけてはいたが気にしていなかった」という描写はありません。
4が不適切: 「触っただけでは気づかなかった」のではなく、触覚で気づいたことが始まりでした。
(エ):線4「これまで感じたことのない喜びだった。」とあるが、そのときの「僕」を説明したものと して最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 指墨画に苦手意識を持っていた「水帆」が絵を描き上げたことに心を打たれたのと同時に、言葉にできないシイタケの生命感まで、視覚を通して感じ取っている様子を目撃し圧倒されている。
2 「水帆」が触った感触を通して形を超えたものを感じ取ったことを嬉しく思うとともに、感じ取ったものをのめり込むようにして表現した絵が、描く喜びで満たされていることに感動している。
3 たった一言で複雑な感覚をわかりやすく表現した、「水帆」の言葉選びの正確さに感心したことに加え、指墨画の魅力に気づいて絵を描くことに喜びを感じている姿を見て感慨にひたっている。
4 「水帆」が自分の感覚を使ってシイタケそのものを捉えたことを喜ばしく思いつつ、最初は歪に描かれていたシイタケの形が徐々に整っていく過程を見て、子どもの成長の速さに感激している。
解答 : 2
解説 :2が適切: 水帆ちゃんが触覚を通して形を超えた生命感を感じ取り、それを夢中で表現している姿、そして絵に描く喜びが溢れていることに「僕」が感動したからです。
1が不適切: 生命感を「視覚を通して」感じ取ったのではなく、触覚が起点でした。
3が不適切: 「僕」は言葉の「正確さ」に感心したのではなく、その裏にある複雑な感覚に喜びました。
4が不適切: 絵の形が「徐々に整っていく」という描写はありませんでした。
(オ):線「忘れちゃうよ。どんな大切なこともね。」とあるが、ここでの「僕」の気持ちをふまえて、 この部分を朗読するとき、どのように読むのがよいか。最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 背教わった大事な言葉を忘れていたことを素直に伝えた上で、「水帆」には絵を描くことを生き生きと楽しむために、今教えた語句の響きをずっと覚えていてほしいという思いを込めて読む。
2 大人も完璧ではないことを明かした上で、生き生きとした線を引いたり絵を楽しんだりすることを、 幼くてまだ何も知らない「水戦」もいつか経験してもらいたいと願っているように読む。
3 自分の記憶力が幼い子どもより劣っていることを情けなく思いつつ、生き生きとした線で描いたり 楽しいと感じたりすることが最も大切だということを、「水帆」に訴えかけるように読む。
4 とても大事な物事ですら忘れていってしまうということを認めつつ、楽しんで生き生きと描くことが一番大切だということを思い出せたのは、「水帆」のおかげだという思いを込めて読む。
解答 : 4
解説 :4が適切: 大事なことでも忘れることがあると認めつつ、水帆ちゃんのおかげで、絵を描く上で一番大切なことを思い出せたという感謝の気持ちが込められています。
1が不適切: 「僕」は言葉そのものを覚えてほしいとは言っていません。
2が不適切: 水帆ちゃんはすでに「生き生きと楽しむこと」を経験し始めています。
3が不適切: 「情けなく思いつつ」という負の感情は、「僕」の喜びと合いません。
(カ):この文章について述べたものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 「僕」との会話を通して指墨画に興味を持った「水帆」が、教えられた技法を忠実に守ることで、きれいな線が描けるようになっていく様子を、指墨画ならではの表現の特徴をふまえて描いている。
2 指で絵を描かせたい「僕」と筆で表現することを好む「水帆」という相反する二人が、言葉を尽くして思いを伝え合うことで、わだかまりを解消していく様子を、 わだかまりを解消していく様子を、二人のやり取りを軸に描いている。
3 水墨画を教える「僕」が、指で絵を描くことを通して成長していく「水帆」と接することによって、 絵を描く上で大切なことと向き合っていく様子を、仕草や表情に関する表現を交えつつ描いている。
4 水墨画の魅力を子どもたちに伝えたい「僕」が、自由にシイタケを表現する「水帆」の姿を見ることによって、形を正確に描く必要はないと気づいていく様子を、指を用いる場面を中心に描いている。
解答 : 3
解説 :3が適切: 水墨画を教える「僕」が、指で絵を描くことを通して成長する水帆ちゃんとの交流を通じて、絵を描く上で大切なことと向き合っていく様子が、仕草や表情を交えて描かれています。
1が不適切: 「きれいな線」を目指したり、技法を「忠実に守る」描写はありません。
2が不適切: 「僕」と水帆ちゃんの間に「わだかまり」があったわけではありません。
4が不適切: 「僕」は元々、形にこだわる必要はないと考えていました。
■大問3
(ア):次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
〈私〉をデザインする
多かれ少なかれ、じつは誰でもやっていることである。
たとえば、ファッションに興味がある人なら、服装のかっこよさや美しいだけでなく、それが相手に与える印象をも考慮するだろう。ファッションを変えることで、自己をデザインするのだ。あまり試したことのない系統の服を着て、自分の新しいイメージを発見する。アクセサリーやカバンで気分を上げる。メイクをする人なら、メイクの仕方によって〈私〉の印象は大きく異なる、ということを知っているはずだ。
それだけではない。あまり意識することはないかもしれないが、私たちは会う人によって少しずつ自己を調整している。家族と休日を過ごす私、友達と酒を飲む私、大学で教える私、駅員さんに乗り場を聞く私、編集者と話し込む私・・・。どれも同じ私だが、それぞれちょっとずつニュアンスが違う。自己デザイン志向は、誰もが普段何気なくやっていることであり、もしまったくデザインできないとしたら、これは逆に、TPOをわきまえていない、ということになりかねない。
とはいえ、1自己デザインには限度があるだろう。他者の視線をいつも気にして、その利害関係だけに関心を持ち、〈私〉の見せ方を柔軟に変えているとしたら、これはよく言えば「世渡り上手」、悪く言えば「裏表のある人」だ。特に、〈私〉をうまくデザインすることで、他者からの承認や評価を自覚的に勝ち取ろうとしている人は、傍目から見るとあまり信用できない。というのも、その言葉や態度は、何かしらの実利に結び付いた演出にすぎないのではないか、という疑念がつねに出てくるからである。自己デザインに凝りすぎるあまり、他者からの不信を買っているとしたら、これはある意味では、自己デザインの失敗だとも言える。何事も自然なバランスが肝要である。
では、自己デザイン志向が遺憾なく発揮されるのは、どのような場所だろうか。そう問いを立ててみると、現実世界での諸々の制約に比べて、サイバースペースでは自己デザインが格段に自由かつ容易である、ということがわかる。学校ではシャイで、友達に話しかけⅠられるとすぐにオドオドしてしまう人でも、SNSでは打って変わって強烈な政治批判を繰り広げる。どれだけかっこよく見せようとしても、現実世界の身体には限界があるが、メタバースのアバターは好きなように作りこむことができる。
[A]、SNSやメタバースは、自己デザイン志向がおのずから優位になる場所なのだ(ただし、メタバースでのアバターが徐々に〈私〉に近づいていく、という興味深い現象もある)。
自己デザイン志向が優位になる空間で生起する承認関係や了解関係は、うまくデザインされた〈私〉同士が取り結ぶものとなるだろう。そして、現実世界の制約を打ち破るこの柔軟な可塑性は、新しい自己意識を関係意識を、それぞれの〈私〉にもたらす。というのも、〈私〉は何者なのかを〈私〉が決められるからである。2ここには、ポジティブな可能性がある。
たとえば、哲学の本の情報をSNSで流し続ければ、〈私〉を哲学好きとして演出することができるし、同じように哲学好きとしてデザインされた他の〈私〉と仲良くなれる。もちろん、ほとんどの場合、実際に哲学が好きな人たちなのだが、重要なのは、他の部分には目をつむって≪現実世界で対面したら、声の大きい威圧的な人かもしれない≫哲学という一点でつながっていける、ということである。つまり、デザインとデザインが嚙み合えば、他の要素は無視できるのだ。ちなみに、私はこのことを基本的によいことだと考えていて、また、楽しいことだとも思っている。
VRの研究をしている学生がこんな話をしてくれた。VRの世界では、人間だけではなく、蜘蛛や鉛筆になることもできる、というのである。たとえば、蜘蛛になってVR空間に入っていけば、巣を張って蝶を待ち伏せしたりする。鉛筆になったら、誰かの手に持たれて、頭を紙に引きずられるのだろうか。学生によると、現実の身体たはまったく異なる身体性に最初は戸惑うが、VRを体験し続けることで、少しずつ慣れてくるらしい。そうして、徐々に蜘蛛の欲望を生きるようになる、というのだ。
蜘蛛の身体を手に入れることで、その欲望を生きるようになる――これはいわば「メタモルフォーゼの 快楽」である。(物理的)身体の変貌によって、欲望が変容する。八本の足を自在に操り、巣に蝶がかか るのを待つ。人間にはない緊張感である。それは「変身」であり、しかも空想の中ではなく、その変容を 現に――〈私)の身体として―――体験することができるのだ。身体と欲望の劇的な変化を味わえるなんて、 それは〈私〉の新しい存在可能を開いている、と言えるかもしれない。
[B]〈私〉を自由にデザインするという発想は、〈私)の存在をよく分からないものにすること でもある。〈私〉の姿形や性格をどうにでも変えられるなら、それはいわば粘土みたいなもので、そこに は(私)の形象がいつでも自由に潰されて、作り変えられる可能性が伴う。だとすれば、むしろ3デザイン できない部分があるからこそ、〈私〉は〈私〉の存在が確かにそこにある、という手触りを感じられる、 とも言えそうだ。
つまり、こうだ。〈私〉の自由にはならないものや、自己デザイン志向が力を及ぼせないものこそが、〈私〉の存在感に一役買っている。その一つが、〈私〉の抱える「弱さ」や「脆さ」なのだ。それは、デザインしきれない〈私〉の存在を指示するからである。
もちろん、新しい自分になろうと努力することは、重要である。〈私〉は変わっていける。誰でも関係性の中で〈私〉を修正しようと試みるし、新しくデザインされた〈私〉によって、楽しく幸せに生きるこ とができるなら、自己デザインは有用なツールとなる。この可能性を否定するつもりはない。認識も存在も変わるのが必然なのだ。
ところが、自己デザイン志向の自由度が高すぎる空間では、〈私〉と他の〈私〉の境界線は極めて曖昧であり、ところが、自己デザイン志向の自由度が高すぎる空間では、〈私)と他の(私)の境界線は極めて暖味であり、その空間における承認や了解はうまくデザインされた〈私〉―――場合によっては、うまくデザインした〈私〉のこともあるかもしれないが――に対するものである。何よりもそれは、お手軽な変身であり、変わろうとする努力の痕跡を残さない。一言でいえば、どうとでも演出できる複数の〈私〉が取り結ぶ関係性なのである。こうした関係にはまり込んで、現実世界にいる〈私〉の有限性をいつまでも放っておくなら、〈私〉がどういう存在なのかが分からなくなる。
〈私〉の存在の実在性は、自己デザイン志向に対する〈私〉の抵抗とその摩擦に相関するのだから。変身した後でもなお、そこに変身前の〈私〉から引き継いでいるものを見出せるなら、それこそが〈私〉の自由にはならない〈私〉の存在を示唆するのだ。
デザインの可能性は無限である。先に述べた通り、デザインされた〈私〉になることで、これまでにはない生き方ができるのだとしたら、その「無限性」は実存の新しい可能性を切り拓くだろう。だが、そこ にデザインしきれない〈私〉の「有限性」が際立ってこなければ、〈私〉の内実はⅡ希薄にならざるをえな い。自己デザイン志向が、どこかで〈私〉の有限性に突き当たるからこそ、〈私〉は〈私〉ではないもの との間でバランスを取ることができるのだ。
ならば、4自己デザインに限界が見えてきたときには、その地平に〈私〉の存在が現われている、とも言える。あるいは、こうである。すなわち、デザインされた〈私〉同士の関係から抜け出せなくなったときに戻って来るべき場所が、どうにも変えようのない〈私〉の有限性にほかならない、と。
〈私〉には弱さや脆さがあること、すなわち、〈私〉は不完全で傷つきやすい存在であること――サイバースペースはこのことから目をそらし、別様に振る舞うことを可能にする。ところで、言うまでもなく、〈私〉の弱さや脆さを過剰に演出することも自己デザインの一つである。自己デザイン志向が優位になる サイバースペースで過ごしすぎると、〈私〉の輪郭が曖昧になっていくのは、当然の帰結なのだ。
デザインされたつながりが広がれば広がるほど、いわれのない疲労と孤独に襲われるのは、デザインさ れた他者による、デザインされた〈私〉の了解と承認が意識を埋め尽くして、デザインできない〈私〉の 存在が持ちこたえられないからである。しかし、これは、〈私〉の絶対性と有限性を取り戻す絶好の機会 でもある。自己デザインの限界が見えているなら、そこに演出を拒む〈私〉がいるはずなのだから。
(岩内章太郎「〈私〉を取り戻す哲学」から。一部表記を改めたところがある。)
(ア):本文中の[A][B]に入れる話の組み合わせとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 A むしろ Bもし
2 A だから Bしかし
3 A たとえば B なぜなら
4 A ただし Bまた
解答 : 2
解説 :[A]:文章[A]の直前では、サイバースペースでの自己デザインの自由度と容易さについて述べられています。直後には、SNSやメタバースが自己デザイン志向が優位になる場所であることが述べられています。この関係性から、「だから」が最も適切です。
[B]:文章[B]の直前では、「メタモルフォーゼの快楽」として、VR空間での身体の変容と欲望の変化について肯定的に述べられています。一方、[B]の直後では、〈私〉を自由にデザインすることの負の側面、すなわち〈私〉の存在が不明瞭になる可能性について述べられています。これは、前の肯定的な内容とは対照的な関係にあるため、「しかし」が最も適切です。
(イ):本文中の~~線Ⅰの「られる」と同じ意味で用いられている「られる」を含む文を、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 少しの時間なら会議を抜けられる。
3 遠くに住む祖母のことが案じられる。
2 先生が学校の外に出かけられる。
4 困っていたところを兄に助けられる。
解答 : 4
解説 :下線部Iの「られる」は「話しかけられる」とあるので、受身の意味で使われています。選択肢の中で受身の「られる」は4です。兄が助ける行為を受け、自分が助けられているからです。
1 抜けられる:可能
2 出かけられる:尊敬
3 案じられる:自発
(ウ):本文中の~~~線Ⅱの語の対義語として最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1濃厚
2熱望
3 強固
4 傲慢
解答 : 1
解説 :1. 濃厚:密度が濃い、内容が充実している。
2. 熱望:強く望むこと。
3. 強固:堅固でしっかりしていること。
4. 傲慢:おごり高ぶって人を見下すこと。
「希薄」の対義語として、最も適切で内容が充実しているという意味合いを持つのは「濃厚」です。
(エ):線1「自己デザインには限度があるだろう。」とあるが、筆者がそのように述べる理由として最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 自己デザインに夢中になると、時間や場所などをわきまえず振る舞うようになり信用を失うから。
2 自己デザインに時間をかけすぎると、一貫性がなく印象が薄い人物だと思われ信用されないから。
3自己デザインに注力しすぎると、実利を求めた演出ではないかと他者から疑われ不信を招くから。
4 自己デザインに熱中すると、実利のためだと 思われていないか疑念が生じ他者を信じなくなるから。
解答 : 3
解説 :「自己デザインには限度があるだろう。」とある理由について、本文では「自己デザインに凝りすぎるあまり、他者からの不信を買っているとしたら、これはある意味では、自己デザインの失敗だとも言える。何事も自然なバランスが肝要である。」と述べられています。
この部分に最も合致する選択肢は3です。
1:時間や場所をわきまえない行動については述べられていません。
2:一貫性がないことや印象が薄いことについては直接述べられていません。
4:他者を信じなくなることではなく、他者から不信を招くことが理由とされています。
(オ):線2「ここには、ポジティブな可能性がある。」とあるが、それを説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 自己デザインが柔軟にできることによって、デザインされた要素のみで他の〈私〉とつながったり、 身体と欲望が現実ではあり得ない形に変容するさまを味わったりすることが可能になるということ。
2 自由に自己デザインを行うことで、デザインされた要素を通してつながった他の〈私〉に別の要素も受け入れてもらえたり、現実とは異なる身体と欲望を体験したりすることが可能になるということ。
3 自己デザインが思い通りにできることによって、自分と同様のデザインが施された他の〈私〉と関係を結んだり、身体が変容しても人間特有の欲望を持ち続けたりすることが可能になるということ。
4 自己デザインの柔軟性が高まることで、共通の趣味を持つ他の〈私〉と仲良くなったり、現実世界と同様の制約の中でも身体と欲望をデザインすることに挑戦したりすることが可能になるということ。
解答 : 1
解説 :1:デザインされた要素のみで他者とつながる点と、身体と欲望が現実ではあり得ない形に変容するさまを味わえる点、この両方が本文でポジティブな可能性として挙げられています。
2:自己デザインによって他者に別の要素も受け入れてもらえるかは本文では直接触れられていません。「デザインとデザインが噛み合えば、他の要素は無視できる」とあります。
3:身体が変容しても人間特有の欲望を持ち続ける点については、VRでの蜘蛛の例では「蜘蛛の欲望を生きるようになる」とあり、人間特有の欲望に限定されていません。
4:現実世界と同様の制約の中でも身体と欲望をデザインすることに挑戦する、という記述は本文の趣旨(サイバースペースでは制約が少ない)と異なります。
(カ):線3 「デザインできない部分があるからこそ、〈私〉は〈私〉の存在が確かにそこにある、という手触りを感じられる」とあるが、それを説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、 その番号を答えなさい。
1 自分の姿形や性格の中にうまく変更できない要素があることによって、演出による修正が可能な部分が際立ち、〈私〉がどのような可能性を持つ存在なのかを〈私〉自身が自覚できるということ。
2 自分を変えることでどのような自己意識や関係意識がもたらされたとしても、自分の中に演出できないものがあることによって、(私)が存在していることを〈私〉自身が実感できるということ。
3 自分一人では自分を演出しきれないことに気づけば、他者に演出を手助けしてもらうことで初めて新たな〈私〉として存在できるようになるという事実に、〈私〉自身がたどり着けるということ。
4 自分のことを演出する中で、姿形や性格においていくら変更を加えても理想の形には届かない要素が見つかれば、理想を目指して変化し続ける〈私〉の存在を〈私〉 自身が感じ取れるということ。
解答 : 2
解説 :「デザインできない部分があるからこそ、〈私〉は〈私〉の存在が確かにそこにある、という手触りを感じられる」について、本文では以下のように説明されています。
「〈私〉の自由にはならないものや、自己デザイン志向が力を及ぼせないものこそが、〈私〉の存在感に一役買っている。その一つが、〈私〉の抱える『弱さ』や『脆さ』なのだ。それは、デザインしきれない〈私〉の存在を指示するからである。」
「自己デザイン志向の自由度が高すぎる空間では、〈私〉と他の〈私〉の境界線は極めて曖昧であり…自己デザインに限界が見えてきたときには、その地平に〈私〉の存在が現われている、とも言える。あるいは、こうである。すなわち、デザインされた〈私〉同士の関係から抜け出せなくなったときに戻って来るべき場所が、どうにも変えようのない〈私〉の有限性にほかならない、と。」
これらの記述から、自己デザインができない部分、つまり自分の自由にならない有限な部分があるからこそ、自己の存在が明確になり、その実在性を感じられる、という筆者の主張が読み取れます。この主張に最も合致する選択肢は2です。
1:演出による修正が可能な部分が際立つ、という点とは異なります。
3:他者に演出を手助けしてもらうことには触れられていません。
4:理想の形に届かない要素が見つかれば、という点ではなく、自己デザインできない「有限性」がキーワードです。
(キ):線4「自己デザインに限界が見えてきたとき」とあるが、それを説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 自己デザイン志向の自由度が高すぎる空間で関係性を結んだ他の〈私〉に、努力して変身したということを隠すために新たな演出を繰り返し行っていった結果、本来の〈私〉の在り方を見失ったとき。
2 自己デザイン志向が優位になる空間においてデザインされた〈私〉同士の関係を築き、楽しく幸せに生きることを目指して変身を行ったことで、変身前の〈私〉に備わっていた有限性が失われたとき。
3 デザインされた〈私〉同士で関係性を取り結んだものの、いくら自己デザインを繰り返しても他の〈私〉からの了解や承認が得られないことによって、〈私〉の輪郭が徐々に曖昧になっていったとき。
4 自己デザインを行った〈私〉同士の関係にのめり込み、自らの有限性に意識を向けず〈私〉に対する丁解と承認で頭の中が一杯になった結果、〈私〉とは何者なのかが分からなくなっていったとき。
解答 : 2
解説 :問題文より、「自己デザインに限界が見えてきたとき」とは、自己デザインに過度に没頭した結果、自分自身の本来の姿や存在意義を見失い、自己の有限性(デザインできない部分)が曖からになった状態を指すと考えられます。
1: 新たな演出を繰り返すことで本来の〈私〉を見失うという点は当たっていますが、「努力して変身したことを隠すため」という理由は本文にありません。
2: 変身前の〈私〉に備わっていた有限性が失われる、というよりは、有限性を無視することで自己が曖昧になる、というニュアンスです。
3: 他の〈私〉からの了解や承認が得られない、という点ではなく、デザインされた〈私〉への承認ばかりで自己の存在が曖昧になることが問題とされています。
4: 自己デザインを行った〈私〉同士の関係にのめり込み、自らの有限性に意識を向けず、「〈私〉とは何者なのかが分からなくなっていったとき」が、まさに筆者が問題としている「自己デザインの限界」の状態を指します。
(ク):筆者は、本文を通して「弱さや脆さ」とはどのようなものだと考えているか。最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 不完全で傷つきやすいという〈私〉の弱点の表れであり、自己デザインの自由度が高く人と人との境界線が曖昧になりやすい空間においては、〈私〉が存在感を保つために克服する必要のあるものだ。
2 〈私〉の欠点にあたる部分であり目をそらしたくなってしまうが、あえて過剰に演出すれば長所に変えることができるので、〈私〉が強くて傷つかない人間になるためには積極的に利用すべきものだ。
3 サイバースペースにおいても〈私〉が思い通りにデザインできないものであり、自己デザイン志向が優位になることによって広がってきている〈私〉の在り方の可能性を、狭める要因となるものだ。
4 自己デザインを行っても〈私〉の中にあり続けるものであるがゆえに、自己デザイン志向が優位になる空間の中でも、不完全で傷つきやすいという要素によって〈私〉の存在を示してくれるものだ。
解答 : 4
解説 :本文では、「〈私〉の自由にはならないものや、自己デザイン志向が力を及ぼせないものこそが、〈私〉の存在感に一役買っている。その一つが、〈私〉の抱える『弱さ』や『脆さ』なのだ。それは、デザインしきれない〈私〉の存在を指示するからである。」と述べられています。
1: 「克服する必要のあるもの」という否定的な捉え方は本文にありません。むしろ、存在を示すものとして肯定的に捉えられています。
2: 「長所に変えることができる」「積極的に利用すべきもの」といった考えは、本文の趣旨とは異なります。本文では「過剰な演出」は自己デザインの失敗につながるとも示唆しています。
3: 「可能性を狭める要因」という否定的な捉え方は本文にありません。むしろ、存在を示す重要な要素として述べられています。
4: 「自己デザインを行っても〈私〉の中にあり続けるものであるがゆえに」「不完全で傷つきやすいという要素によって〈私〉の存在を示してくれるものだ」という点が、本文の「デザインしきれない〈私〉の存在を指示する」という記述と合致します。
(ケ):本文について説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 自己デザインの自由度が高い空間において、〈私〉に備わる有限性が軽視されているという現状を指摘した上で、自己デザインを行わないありのままの自分でいることの必要性について論じている。
2 自己デザイン志向が力を及ぼせないものと〈私〉の存在との関係性について整理しつつ、自己デザ インを行うにあたっては、自分の弱さや脆さを他者に積極的に見せていくことが重要だと論じている。
3 自己デザインとは何かを確認し、サイバースペース上での自己デザインの可能性と問題点を述べた上で、〈私〉の存在をつかめなくなった際に自身の有限性に着目することの意義について論じている。
4 自己デザインは誰もが行えるものではないということを明らかにする一方で、デザインされた 〈私〉同士が取り結ぶ関係に注目し、サイバースペースで感じる疲労や孤独の原因について論じている。
解答 : 3
解説 :1: 「自己デザインを行わないありのままの自分でいることの必要性」については論じていません。自己デザインの有用性は認めています。
2: 「自分の弱さや脆さを他者に積極的に見せていくこと」が重要だとは述べていません。弱さや脆さが〈私〉の存在を示す要素であるとは述べていますが、積極的な開示を勧めているわけではありません。
3: 上記の本文のまとめと最も合致しています。「自己デザインとは何かを確認し、サイバースペース上での自己デザインの可能性と問題点を述べた上で、〈私〉の存在をつかめなくなった際に自身の有限性に着目することの意義」を論じています。
4: 「自己デザインは誰もが行えるものではない」とは述べていません。むしろ「じつは誰でもやっていることである」と冒頭で述べています。
■大問4
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
ある時徳宗領に沙汰出で来て、地下の公文と相模守と訴陳に番ふことあり。理非懸隔して、公文が申すところ道理なりけれども、奉行・頭人・評定衆、皆、徳宗領にてつて、公文を負かしけるを、青砥左衛門ただ一人、権門にも恐れず、理の当たるところを具に申し立てて、1つひに相模守をぞ負かしける。公文不慮に得利して、所帯に安堵したりけるが、その恩を報ぜんとや思ひけん、銭を三百貫俵に包みて、後ろの山より窃かに青砥左衛門が坪の内へぞ入れたりける。青砥左衛門これを見て大いに怒り、「沙汰の理非を申しつるは、相模殿を思ひ奉る故なり。全く地下の公文を引くに非ず。もし引き出物を取るべくは、上の御悪名を申し留めぬれば、相模殿こそ喜びをばしたまふべけれ。沙汰に勝ちたる公文が引き出物をす べき様なし。」とて、2一銭をもつひに受用せず、遥かに遠き田舎まで持ち送らせてぞ返しける。
またある時、この青砥左衛門夜に入つて出仕をしける。いつも火打ち袋に入れて持ちける銭を十文取りはづして、滑川へぞ落とし入れたり。少事の物なれば、よしさてもあれかしとて行き過ぐべかりしが、以ての外にあわてて、その辺りの町屋へ下人を走らかし、銭五十文を以て松明を十把買ひて、これを灯してつひに十文の銭をぞ求め得たりける。後に人これを聞きて、「十文の銭を求めんとて、五十にて松明を買ふ。3小利大損にて非ずや。」と笑ひければ、青砥左衛門眉をひそめて、「さればこそ御辺達は愚かにて、世の費えをも知らず、民を恵む心なき人なれ。十文の銭はその時求めずは、滑川の底にして永く失ふべし。松明を買ひつる五十の銭は商人の家に留まつて失すべからず。我が損は商人の利なり。彼と我と何の差別かある。かれこれ六十の銭一つも失はざるは、あに所得に非ずや。」と爪弾きをして申しければ、難じて笑ひつる傍の人々、舌を打つてぞ感じける。
(「太平記」から。)
(ア):線1「つひに相模守をぞ負かしける。」とあるが、それを説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 領地を巡る裁判において、身分が高くない「地下の公文」を皆が負けだと判断する中で、「青砥左衛門」だけが「地下の公文」の人柄の良さを詳しく説明した結果、「相模守」が敗れたということ。
2 領地を巡る裁判において、徳宗領であることに遠慮して皆が「地下の公文」の負けだと判断する中で、「青砥左衛門」だけが「地下の公文」の正当性を主張した結果、「相模守」が敗れたということ。
3 領地を巡る裁判において、徳宗領であることを気遣って皆が「地下の公文」を負けとみなす中で、「青砥左衛門」だけが「地下の公文」に同情して救おうとした結果、「相模守」が敗れたということ。
4 領地を巡る裁判において、筋の通った 主張ができずにいた「地下の公文」を皆が負けとみなす中で、「青砥左衛門」だけが堂々と「地下の公文」の立場を認めた結果、「相模守」が敗れたということ。
解答 : 2
解説 :1:間違いです。 本文には「人柄の良さ」について触れられていません。青砥左衛門が重視したのは「理の当たるところ」、つまり道理と正当性です。
2:これが正解です。 奉行や評定衆が徳宗領に忖度して公文を負けにしようとする中、青砥左衛門だけが、公文の主張が道理にかなっていることを毅然と述べ、最終的に相模守を負かした、という本文の内容と完全に一致します。
3:間違いです。 青砥左衛門の行動は「同情」からではなく、あくまで「理の当たるところ」を貫く、という公明正大な態度に基づいています。
4:間違いです。 本文には「公文が申すところ道理なりけれども」とあり、公文の主張は最初から筋が通っていました。青砥左衛門はその道理を代弁したまでです。
(イ):線2「一銭をもつひに受用せず」とあるが、「青砥左衛門」がそのようにした理由として最も適するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 「地下の公文」からの贈り物を受け取ることによって、裁判で不公平な判決が下されていたという事実に「相模守」が気づいてしまうことを恐れたから。
2 対立していた「相模守」の悪評が広がったことを喜んで金銭を贈ってきた「地下の公文」に対し、自己中心的で浅はかな人間だと思い怒りを覚えたから。
3 領地を手に入れた「地下の公文」が贈り物をするべき相手は、裁判を担当した自分ではなく敗訴してしまい悲しい思いをした「相模守」だと思ったから。
4 公平な裁判を行ったことによって「相模守」の方こそ立場が保たれたのであり、「地下の公文」が金銭を贈ってくるのは道理に合わないと考えたから。
解答 : 4
解説 :1:間違いです。青砥左衛門は公平な判決を下したと自負しています。
2:間違いです。怒りの理由は、公文の報恩の仕方が道理に反すると考えたためです。
3:間違いです。相模守に贈るべき、というよりは、自分が受け取るのは筋違いだと考えています。
4:正解です。これが青砥左衛門の行動原理に最も合致です。
(ウ):線3「小利大損にて非ずや。」とあるが、それを説明したものとして最も適するものを次の中から一つ選び、その記号を答えなさい。
1 川に落としてしまった少額の銭を探すために、十把だけ松明を購入した「青砥左衛門」の行動は、 川底の銭を探すには松明の数が少なすぎることからかえって大きな損になっているということ。
2 川に落としてしまった少額の銭を探すために、本来は十文で買えるはずの松明を五十文で購入した 「青砥左衛門」の行動は、支払った金額の多さをふまえると大きな損になっているということ。
3 川に落としてしまった少額の銭を探すために、落とした金額よりも高い額を払って松明を買い求めた「青砥左衛門」の行動は、金銭面から考えるとかえって大きな損になっているということ。
4 川に落としてしまった少額の銭を探すために、夜遅い時間にもかかわらず松明を買い求めた「青砥左衛門」の行動は、店に対する迷惑の大きさをふまえると大きな損になっているということ。
解答 : 3
解説 :1:間違いです。松明の数が不足しているという指摘ではありません。
2:間違いです。松明の定価に関する記述はなく、単純に十文の銭に対し五十文の松明が「高い」と見なされている点にあります。
3:正解です。これが「小利大損」という指摘の核心です。得ようとする利益(十文)に対し、支払った費用(五十文)が大きいという意味です。
4:間違いです。店の迷惑が損益の基準になっているわけではありません。
(エ):本文の内容と一致するものを次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1 「青砥左衛門」は、裁判で権力者を恐れることなく発言したり、一見自分の損失に思われることでも世の中全体の利益であると考えたりするような、自らの利害にとらわれず筋を通す人物だった。
2 「青砥左衛門」は、裁判で不利な立場にいる人物の発言を大事にしたり、川に銭を落とした家来に対して見つけるまで捜索を一緒に行ったりするような、周囲の人間を常に尊重する人物だった。
3 「青砥左衛門」は、裁判を行う中で道理に合わないと感じた意見に反論したり、川に落とした銭を日中から夜にかけて諦めずに探し続けたりするような、常に自分の考えを貫き通す人物だった。
4 「青砥左衛門」は、裁判において大多数が賛同した考えを受け入れたり、自らの損得よりも自分と関わる人物が利益を得られることを優先したりするような、心が広く思いやりのある人物だった。
解答 :1
解説 :1:正解です。 裁判で権力に屈せず道理を述べ、公文からの謝礼を「道理に合わない」と拒否。また、十文の銭と五十文の松明の件では、個人の損得を超えて「世の費え」や「商人の利」という全体的な視点で物事を捉えており、まさに自分の利害にとらわれず筋を通す人物像が描かれています。
2:間違いです。不利な立場の人を助けたのは「道理」によるものであり、単に尊重したからではありません。また、家来と「一緒に」捜索したという記述もなく、松明の購入を命じたのは指示であり、尊重とは異なります。
3:間違いです。「常に自分の考えを貫き通す」という点は一部当たりますが、「日中から夜にかけて諦めずに探し続けた」という記述はありません。夜の出仕時に落とし、その夜のうちに探しています。また、「道理に合わないと感じた意見に反論」はしていますが、それが彼の行動の全てを表現しているわけではありません。
4:間違いです。彼の行動は「道理」に基づいています。「大多数の賛同」を受け入れたわけではなく、むしろ多数に反して道理を主張しました。また、他者の利益を優先したのは、それが「道理」にかなっている場合であり、単なる「思いやり」だけではありません。
■大問5
中学生のKさんは、「目の前にいない友人とのやりとり」において大事なのは、すぐに連絡をとり合うことだと考えているが、他の視点からの考え方も知りたいと思って資料を調べ、二つの文章に着目した。次の【文章1】、【文章2】は、そのときのものである。これらについてあとの問いに答えなさい。
【文章1】
ケータイ、スマホの登場により、これまで私たちを隔てていた物理的な距離は無視しうるものとなった。私たちは、いつでも、どこでも意中の相手とつながる環境を手に入れたのである。しかし、 膨らんだ期待は、それがかなわなかったときの失望感も増幅させる。言い換えると、「つながらないこと」に対する耐久力を大幅に落としてしまう。 たとえば、友だち、またはつきあっている人とつながらない状況を考えてみよう。「常時接続前」の時代であれば、距離の隔たった相手と「つながること」は当たり前ではないので、つながっていない 状況に対する不満や不安は、そう簡単には生じない。
手紙の時代であっても、相手の返信にやきもきすることはあったようだが、一日、二日連絡が来ないことは、それほど気にならなかっただろう。そもそも、手紙の時代にはそれほどの短期間で連絡をとる手段もなかった。 「常時接続」の時代になると、相手と「つながること」が常態になる。人びとが相手とつながること を当然と考えているならば、かりに、目の前にいない誰かとつながらない事態が生じると、その状況に対して強い不満や不安を抱くようになる。
(石田郷「「友だち」から自由になる」から。一部表記を改めたところがある。)
【文章2】
女子学生Aは、大学に入学して一人暮らしになったとき、中学時代の友人と文通を始めた。手紙の内容は「最近縮しかったこと」「気づいたこと」「自分と相手の環境がどう違うかなど、知りたいこと」「共有したい便利な情報」など、LINEでも連絡できることである。より早く連絡できるという点で はLINEが便利である。彼女の相手は、手紙を受け取った嬉しさをいち早く伝えたくてわざわざ LINEで知らせてきたほどだ。 しかし手書きの言葉には、LINEの打ち言葉にないものがある。書き手の筆跡、使う筆記具、消した跡など、書き手が意識していない情報を受け手が読みとることも可能になる。消した痕跡からは、 書き手の心の動きも読み取れるように思えるほどだ。言い換えれば、フォント化された打ち言葉やありきたりの絵文字やスタンプにはない書き手の個性が、文字と手紙には現れるのである。
彼女は便箋の裏に絵を描き添えることもしているのだが、「手元にある可愛い包装紙の絵」や「見てほしいアーティストの似顔絵」など、便箋に書いた内容とは関係がない絵を追伸のような感覚で描いている。書きたいことがたくさんあって、枚数が五、六枚になってしまった時にふと裏面が寂しいことに気がついて、何か描いて白紙の部分を埋めようとしたのが始まりだそうだ。それはスタンプの絵 文字にはない、彼女の個性や手間暇かけた痕跡が残ったものである。そのような手書きの手紙をやりとりすること、それは、交換する両者が、互いにかけがえのない特別な関係にあることを表している。 そのためこの女子学生は自分の気に入った便箋を用意し、「文豪のように」 万年筆で手紙を書いて、 LINEで同じ内容を送った場合とは異なる印象や「特別感」を出そうとしている。
(出口「声と文字の人類学」から。一部表記を改めたところがある。)
(ア):Kさんは事前に自分の考えを書いた上で、【文章1】と【文章2】を読み、内容を次のようにまとめ た。【Kさんのメモ】中の Ⅱに入れる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
【Kさんのメモ】
「自分の考え 」目の前にいない友人とのやりとりにおいて大事なのは、すぐに連絡をとり合うことであり、 そのためにはモバイル端末を用いるのがよい。 本当にそうだろうか?
【文章1】…携帯電話やスマートフォンといったモバイル端末がもたらした気持ちの変化。
[Ⅰ]という期待が高まったことで、思った通りにならなかったときの失望感が増幅した。
一方、「常時接続」でない手紙の時代には、一日、二日連絡が来ないことはそれほど気にならなかった。
【文章2】…文通で友人との仲を深める女子学生の話を通して見える、手紙でのやりとりがもつ力。
手書きの言葉からは、筆跡、使う筆記具、消した跡などの、[2] を読みとることもできる。
→友人と手紙でやりとりすることは、モバイル端末でやりとりすることとは違った意味合いをもつ。
1 Ⅰ返信がなくてもやきもきしなくなるだろう Ⅱ自然と表れた書き手の心の動き
2 Ⅰ常に相手とつながる環境が手に入るだろう Ⅱ書き手が意図的に示していること
3 Ⅰいつでもどこでも相手とやりとりができる Ⅱ書き手が無意識に発した情報
4 Ⅰ携帯電話やスマートフォンを常に操作できる Ⅱ自分と書き手との小さな違い
解答 :3
解説 :【文章1】の空欄 I について: 【文章1】では、ケータイやスマホの登場により「いつでも、どこでも意中の相手とつながる環境を手に入れた」とあります。このことから、モバイル端末がもたらした「期待」として最も適切なのは、「いつでもどこでも相手とやりとりができる」ことです。これがかなわないと失望感が生まれるという文脈に合致します。
【文章2】の空欄 II について: 【文章2】では、手書きの言葉から「書き手の筆跡、使う筆記具、消した跡など、書き手が意識していない情報を受け手が読みとることも可能になる」と述べられています。そして、「消した痕跡からは、書き手の心の動きも読み取れるように思える」ともあります。これらを総合すると、手紙から読み取れるのは「書き手が無意識に発した情報」が最も適しています。
(イ):Kさんは【文章1】と【文章2】を読んで考えたことを次のようにまとめた。【Kさんのまとめ】中『 』の に適することばを、あとの①~④の条件を満たして書きなさい。
【Kさんのまとめ】
【文章1】には、モバイル端末が普及したことで物理的な距離は無視できるものになったが、相手とつながらない事態が生じたときに強い不安や不満を感じるようになったと述べられている。私も、すぐに連絡をとり合うことを重視していたので、連絡がないときの不安が強まっていたと感じた。一方、 「手紙の時代には、すぐに連絡が来なくてもあまり気にならなかっただろうと述べられているが、「常時接続」の時代となっても、届くまでに時間を要する手紙がなぜ用いられているのか気になった。
【文章2】からは、手紙でのやりとりにはモバイル端末でのやりとりとは異なるよさがあると感じた。
「まず、手紙でのやりとりが時間を要するのは、手紙を運ぶのに日数がかかるだけでなく、書き手が時間をかけて書いているからだと気づいた。そして、手間暇をかけた痕跡や直筆によって現れる書き手の個性が、手紙からは読みとれると知った。そのような手紙をやりとりすることで、相手を大切に思っていることが互いに伝わるということを、手紙を書く人びとは大事にしているのだろう。
以上のことから、手紙でのやりとりではできないことと手紙でのやりとりだからこそできることが、それぞれあるとわかった。つまり、手紙でのやりとりには、『 』という特徴があるといえる。今後は、状況に応じてモバイル端末と手紙を使い分け、友人のやりとりをもっと楽しんでいきたい。
①書き出しの「手紙でのやりとりには、」という語句に続けて書き、文末のという特徴があるといえるという語句につながる一文となるように書くこと。
②書き出しと文末の語句の間の文字数が三十字以上四十字以内となるように書くこと。
③【文章】と【文章2】の内容に触れていること。
④「短期間」「特別」という二つの語句を、どちらもそのまま用いること。
解答 :(例)手紙でのやりとりには、『短期間で、連絡をとることはできないが、相手と特別な関係にあることを表すことができる』という特徴があるといえる。
解説 :3つのポイント
・「短期間での連絡には不向きだが」: これは【文章1】で述べられている、手紙が「常時接続」のモバイル端末とは異なり、すぐに連絡が取れないという特徴に触れています。
・「書き手の個性や手間暇が伝わり」: これは【文章2】で強調されている、手書きの言葉や絵から読み取れる筆跡、筆記具、消した跡、そして手間暇かけた痕跡が、書き手の個性を示すという点に言及しています。
・「相手との特別な関係を築き深める」: これも【文章2】の中心的なメッセージであり、手紙のやりとりが「互いにかけがえのない特別な関係にあることを表している」という部分に対応します。