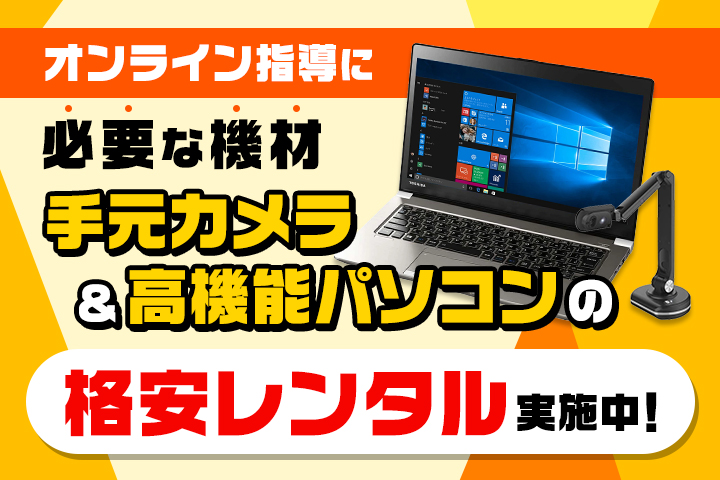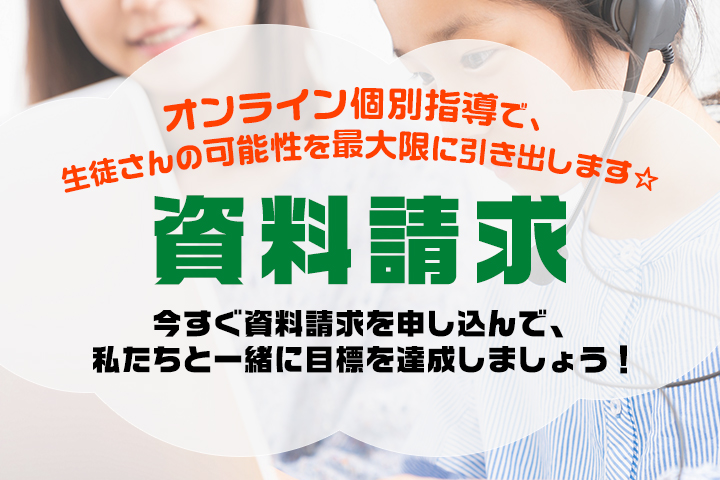■問題PDF
令和7年度_学力検査問題過去問【東京】- 国語
■目次
大問1
大問2
大問3
大問4
大問5
■大問1
1−1:次の各文の―を付けた漢字の読みがなを書け。 玄関に美しい梅の花を飾る。
解答 :かざ る
1−2:陸上選手の跳躍に拍手が起こる。
解答 :ちょうやく
1−3:物理学の進歩は社会の発展に貢献した。
解答 : こうけん
1−4:少しずつ水を混ぜて紙粘土を柔らかくする。
解答 :ま ぜて
1−5:宇宙飛行士が喝采を浴びながら迎えられる。
解答 : かっさい
■大問2
2−1:次の各文の―を付けたかたかなの部分に当たる漢字を楷書で書け。 高原の湖が霧にツツまれる。
解答 : 包 まれる
2−2:熱い思いを胸にヒめて大会へ向かう。
解答 : 秘 めて
2−3:母のキョウリは夏みかんの名産地だ。
解答 :郷里
2−4:長距離走で前回よりも記録をチヂめる。
解答 :縮 める
2−5:海外留学のためにリョケンの発行を申請する。
解答 : 旅券
■大問3
3−1:次の文章を読んで、あとの各問に答えよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小学六年生の「ぼく(あおば)」と同級生の梛(なぎ)は、アオナギと名付けたオオタカのヒナの巣立ちを、鳥の研究者で自然保護活動をしている葛城(かつらぎ)たちと共に見守っている。
※本文は掲載許諾申請中のため掲載がありません。
※ルビがふってあるものは漢字のあとに括弧で示しています。
(にしがきようこ「アオナギの巣立つ森では」による)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)そのアオナギと視線が合った、と思ったその瞬間、ぼくの心はズキュンと射抜かれた。とあるが、この表現について述べたものとして最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア アオナギの姿におののく「ぼく」の様子と威嚇するアオナギの様子とを、対照的に描き分けることで表現している。
イ ヒナだった頃のアオナギの姿を思い出し感慨にふける「ぼく」の様子を、擬音語を用いて表現している。
ウ アオナギの巣立ちの瞬間を待ちわびている「ぼく」の様子を、アオナギの視点から客観的に表現している。
エ 全身を現したアオナギと視線を交わした途端に心揺さぶられた「ぼく」の様子を、たとえを用いて表現している。
解答 : エ
3−2:(2)ぼくの隣で梛がつぶやいた。とあるが、この表現から読み取れる梛の様子として最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア アオナギとの別れがあっけなかったので、別れをどのように受け止めているのか「ぼく」に聞いてみようと思っている様子。
イ アオナギが飛び立つ瞬間に自分たちのほうを向いたかどうかが気になって、「ぼく」に確かめようとしている様子。
ウ アオナギが巣立った後の喪失感を、巣立ちを一緒に見守った「ぼく」と分かち合おうとしている様子。
エ アオナギとの別れに感傷的になりながらも、自分よりももっと悲しんでいる「ぼく」を精一杯励まそうとしている様子。
解答 :ウ
3−3:(3)葛城さんが鼻の横を指でかきながらぼくを見ている。とあるが、この表現から読み取れる葛城の様子として最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア 「ぼく」のテントでの行動や野生動物についての発言を振り返りながら、「ぼく」への興味を深めている様子。
イ 野生動物を見られなかった不満を一方的に伝えてきた「ぼく」をなだめ、「ぼく」の気持ちに寄り添おうとしている様子。
ウ 「ぼく」が野生動物を観察していたと思っていたが事実ではなかったと分かり、どうやって励ましたらよいかと迷っている様子。
エ 野生動物を見た記憶がないという「ぼく」の話から、貴重な機会を逃して落ち込んでいないかと心配している様子。
解答 : ア
3−4:(4)ぼくは息を吸って、大きくうなずいた。とあるが、「ぼく」が「息を吸って、大きくうなずいた」わけとして最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア 梛の言葉から、アオナギとの別れを受け入れられなかった自分を情けなく思い、梛に心配をかけたことも申し訳なく思ったから。
イ 梛の言葉を受けて、アオナギやその子孫にまた会えると自分を納得させ、アオナギとの別れの寂しさを振り払おうと思ったから。
ウ 梛の言葉を聞いて、無事に巣立ったアオナギをいつまでも気にするよりも、森で過ごす今の時間を大切にしたいと思ったから。
エ 梛の言葉から、アオナギの巣立ちを見守った人たちとの別れが近付いているのを実感し、立派な態度で別れようと思ったから
解答 : イ
3−5:(5)葛城さんが言い終わる前に、ぼくは叫んでいた。とあるが、このときの「ぼく」の気持ちに最も近いのは、次のうちではどれか。
ア 願ってもない誘いに戸惑いつつも山で生活する好機を逃さないように、大声を出して自分自身を勇気付けようという気持ち。
イ 山に誘われたことに対する感謝の思いを、アオナギの巣立ちを一緒に見守った人たちに伝えたいという気持ち。
ウ 葛城の言葉に素早く反応して意思表示することで、山で生活することを祖父に認めさせたいと思う気持ち。
エ 予想もしていなかった葛城からの誘いを受けて、山で生活することへの喜びが湧き上がって抑えきれない気持ち。
解答 :エ
■大問4
4−1:次の文章を読んで、あとの各問に答えよ。(*印の付いている言葉には、本文のあとに〔注〕がある。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本文は掲載許諾申請中のため掲載がありません。
(中田星矢「文化のバトンを受け継ぐコミュニケーション」(一部改変)による)
〔注〕
ヘルマン―― ドイツの霊長類学者。
嗜好(しこう)―― 人それぞれの、飲み物や食べ物等の好み。
ワシレフスキー―― アメリカの進化人類学者。
一子相伝(いっしそうでん)―― 学術・技芸などを一人だけに伝えて他に漏らさないこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)石のハンマーを持っているチンパンジーとスマートフォンを持っている人間を見比べて、人間の方が賢いというのはフェアな比較ではないように思われます。とあるが、筆者がこのように述べたのはなぜか。次のうちから最も適切なものを選べ。
ア チンパンジーと人間の賢さは、道具の使い方ではなく高度な仕組みを理解できるかどうかで比較するべきであると考えているから。
イ 石のハンマーとスマートフォンだけで賢さを判断するのは不十分であり、他の道具も加えて比較するべきであると考えているから。
ウ チンパンジーと人間の賢さは、持っている道具を基準に判断するのではなく個々の能力で比較するべきであると考えているから。
エ チンパンジーも筆者もスマートフォンの作り方がわからないため、作り方がわかる道具で賢さを比較するべきであると考えているから。
解答 :ウ
4−2:(2)社会的学習によって他者から学ぶことこそが、現代に見られる高度な技術を支える鍵なのです。とはどういうことか。次のうちから最も適切なものを選べ。
ア 因果関係や数量概念を理解する能力が、高度な技術を継承したり伝達したりするために必要不可欠だということ。
イ 他者が製作した道具を使いこなす能力が、同じ道具を一から忠実に作り直すために必要不可欠だということ。
ウ 道具の使い方を他者に伝達する能力が、さらに便利な道具を開発し続けるために必要不可欠だということ。
エ 他者の行動や様子を捉えて模倣する能力が、世代を超えて技術を発展させていくために必要不可欠だということ。
解答 : エ
4−3:この文章の構成における第七段の役割を説明したものとして最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア それまでに述べた内容を整理した上で、さらに説明を付け加え、この後に紹介する具体例へと論をつなげている。
イ それまでに述べた内容に関して、根拠となる事例を付け加え、この後に述べる主張の前提を明らかにしている。
ウ それまでに述べた内容に対して、対照的な意見を付け加え、この後に続く話題への転換を図っている。
エ それまでに述べた内容をまとめた上で、筆者の体験を付け加え、この後に引き継がれる自説の妥当性を強調している。
解答 :ア
4−4:(3)実験条件を異なる社会として考えてみると、技術の細部まで伝達する社会とそうでない社会では、前者だけが長い年月を経て非常に優れた技術まで到達できることが示唆されたのです。とあるが、「前者だけが長い年月を経て非常に優れた技術まで到達できることが示唆された」と筆者が述べたのはなぜか。次のうちから最も適切なものを選べ。
ア 作業工程と完成品の両方を観察した参加者だけが技術を応用することができ、技術革新を達成すると示されたから。
イ 作業工程を観察できた参加者だけが前世代の製作技術を学ぶことができ、技術の改良と継承が続くと示されたから。
ウ 自力で試行錯誤した参加者だけが技術を磨き続けることができ、自分自身の力で高い技術を得られると示されたから。
エ 前世代の完成品を観察した参加者だけが同様の技術を再現することができ、技術の継承が行われると示されたから。
解答 : イ
4−5:国語の授業でこの文章を読んだ後、「文化を受け継ぎ発展させること」というテーマで自分の意見を発表することになった。このときにあなたが話す言葉を具体的な体験や見聞も含めて二百字以内で書け。なお、書き出しや改行の際の空欄、「、」や「。」や「などもそれぞれ字数に数えよ。
解説 : 必須のポイント
〇テーマ「文化を受け継ぎ発展させること」に即した自分の意見、主張が書かれていること。
〇本文中の筆者の意見を的確に捉え、その主張を踏まえていること。
〇自分の意見、主張の根拠となる具体的な体験や見聞について書かれていること。
■大問5
5−1:次のAは、和歌に関する対談の一部である。Bは、対談中で話題にしている藤原俊成(ふじわらのしゅんぜい)が書いた「六百番歌合(ろっぴゃくばんうたあわせ)」の解説文であり、[ ]内の文章は引用された「六百番歌合」の原文である。また、[ ]内の文章は原文の現代語訳である。これらの文章を読んで、あとの各問に答えよ。(*印の付いている言葉には、本文のあとに〔注〕がある。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本文は掲載許諾申請中のため掲載がありません。
A (河合隼雄、池田利夫「松浦宮物語と藤原定家」による)
B (前田雅之「なぜ古典を勉強するのか」による)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冬上十三番 枯野 左の勝ち 女房(にょうぼう)(藤原良経(ふじわらのよしつね)(の歌)
秋の間に見た美しい景色を何に残したらよいだろうか。秋の間多くの花が咲いた草の原も枯れて見渡す限り同じ景色に変わってしまっている。
右 隆信(の歌)
霜枯れの野辺の荒れ果てた様子に目を留めない人が秋の寂しい景色には心をとめたのであろうか。
右の歌の作者(隆信)は、(良経の歌の)「草の原」は歌に使う言葉として聞きなれない(のでよくない)と申します。左の歌の作者(良経)は右の歌は古めかしい(のでよくない)と申します。判定役(俊成)としていうと、左の歌の「何に残さん草の原」というのが優艶でございます。右の歌の作者が「草の原」を非難したのは非常に不満です。紫式部は歌を詠むより物語を書く力が格段に優れています。その上、(源氏物語の花の)宴の巻は、特に優美な話です。源氏物語を見ていない歌詠みはとても残念です。右の歌の内容と言葉は悪くありません。とはいうものの、ありふれた平凡な歌です。左の歌の方が素晴らしく、勝ちというべきです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔注〕
松浦宮(まつうらのみや)――平安時代末期から鎌倉時代の歌人である藤原定家による物語『松浦宮物語』のこと。
萩谷朴(はぎたにぼく)―― 国文学者。
藤原良経(ふじわらのよしつね)―― 平安時代中期の歌人。
朧月夜(おぼろづきよ)――『源氏物語』の登場人物。女性。
うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ――つらい身の私が、このまま消えてしまったら、名を知らないからといって、あなたは草の原を分けてでも私を尋ねようとはなさらないでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Aの中のを付けたア~エの「ない」のうち、他と意味・用法の異なるものを一つ選び、記号で答えよ。
解答 : エ
5−2:(1)河合さんの発言のこの対談における役割を説明したものとして最も適切なものは、次のうちではどれか。 ア 池田さんの『源氏』における歌の説明に疑問をもち『古今集』での歌の選び方を尋ねることで、話題を整理している。 イ 『源氏』の歌の作り方について池田さんと共通理解を得られたことで、対談の内容を深めるために話題を『古今集』に転換している。 ウ 歌を詠む上での『源氏』と『古今集』の重要性について池田さんと共通理解を得たことで、自説を述べるきっかけを作っている。 エ 池田さんの『源氏』の説明に疑問をもち『古今集』との共通点について質問することで、次の発言を促している。
解答 : イ
5−3:(2)むしろ意識的に定家らしくなくつくっているように見えますね。とあるが、ここでいう「意識的に定家らしくなくつくっている」を説明したものとして最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア 定家は『万葉集』の時代を想像して書いた『松浦宮』の作中において、自身の作風とは異なる万葉風の歌も詠んだということ。
イ 定家は『万葉集』を批判するために書いた『松浦宮』の作中において、万葉風とは違う作風の歌を詠んだということ。
ウ 定家は『万葉集』のよさに改めて気付き、『松浦宮』の作中で徐々に万葉風の歌を増やしていったということ。
エ 定家は『万葉集』の歌ごころが想像できるようになったからこそ、『松浦宮』の作中で万葉風とは異なる歌のみを詠んだということ。
解答 : ア
5−4:(3)非難するのはとあるが、Bの原文において「非難するのは」に相当する部分はどこか。次のうちから最も適切なものを選べ。
ア 聞きよからず
イ 艶にこそ
ウ 難申之条
エ 悪しくは見えざるにや
解答 :ウ
5−5:A及びBでは共通して『源氏物語』を歌人の必読の物語だとする俊成の考えが示されているが、A及びBのそれぞれで述べられた、歌人にとっての『源氏物語』の価値を説明したものとして最も適切なのは、次のうちではどれか。
ア Aでは『古今集』を読み解くのに適している作品だと述べられており、Bでは歌合の判定の根拠になるほど優美な歌が含まれる作品だと述べられている。
イ Aでは歌が詠まれる状況や心の動きを理解できる作品だと述べられており、Bでは歌を含む物語によって優美な世界を表現できる人物が書いた作品だと述べられている。
ウ Aでは作中の歌を通じて『万葉集』の時代の人の心を理解できる作品だと述べられており、Bでは優美な歌合の様子が現代の私たちにもわかる作品だと述べられている。
エ Aでは歌の技法を理解するのに適している作品だと述べられており、Bでは歌集としての評価以上に優美な物語として高く評価されている作品だと述べられている。
解答 :イ